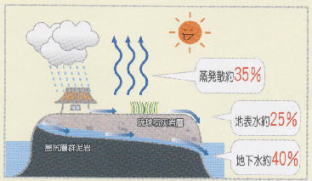「県営かんがい排水事業与勝地区」の概要
与勝地区は、沖縄本島中部の与勝半島に位置し、勝連町・与那城町・具志川市にまたがる
農地面積225haのさとうきびを基幹作物とする畑地帯です。地区内では、地形や地質的な条
件から地表水が乏しく、充分な農業用水の確保が困難でかんがい施設も未整備なことから、
恒常的な干ばつ被害に見舞われています。
そのため本事業では、半島の地下を流れる豊富な水を利用することで、安定的な農業用水
の供給が実現するよう、平成18年度の完成を目指して地下ダムを新設するとともに配水施設
を整備します。これにより、農作物の増収及び品質の向上を図るとともに、野菜・花卉等の高
付加価値作物への転換を可能とし、農業経営の安定 に向けた基礎案件を確立します。
与勝半島の勝連城跡より南側では、会体
に急斜面に囲まれた台地状の地形を成し、
灰色の島尻層群泥岩(通称:クチヤ)を不透
水性基盤として、その上に水が浸透しやす
い透水層の琉球層群(主に琉球石灰岩)が
載う地質構成となっています。これに起因
して、2,000mmを越える年間降水量の内、
地表を流出する水ほ会体の25%こすぎず、
大気中への蒸発散を除く残り40%以上の雨
は、石灰岩を浸透して地下水となっていま
す。このため人々は、昔から井戸(カー)
や平安名ガーなどの湧水を大切に守り、飲
用をはじめとする生活用水に使用するとと
もに、その残りを農業用水に活用してきま
したが、干ばつ時には深刻な水不足に悩ま
され続けてきました。
では、多量の地下水はどこにあるのでし
よう? これまでの調査から、地区一帯の
琉球石灰岩下に地下の谷が存在し、ほぼ
県道8号線に治って大規模な『地下の川』が
平敷屋沖の海へと流下していることが判明し
ました。この地下の構造を生かして地下ダ
ムを建設すうことで、安定的な農業用水源を
確保すうことが可能となったのです。
与勝半島は、新第三紀
鮮新世の島尻層群泥岩を
不透水性基盤とし、半島
中央・軸方向に形成され
た基盤の地下谷を埋積し
て、透水層の第四紀更新
世琉球層群が載る地質構
成となっています。(琉球
層群最下部の勝連層は、
知念砂岩相当層で一部を
除き不透水層)各層の透
水性状は、平均空隙率
8.4%の琉球石灰岩で透水
係数は5×1/100cm/sec、
島尻層群泥岩で1×1/1
000000cm/sec以下と
なっています。
地層の様子
与勝地下ダムの集水域で
ある勝連城跡より南側でほ、
不透水暦の島尻層群泥岩
が透水層の琉球石灰岩に
覆われています。
(透水層最大層厚90m)
不透水層の形状
集水域の琉球石灰岩を剥ぎ
取ると、不透水層上面に形成
された地下谷があらわれ、降
雨量の40%がこの『地下の川』
を流下しています。
(基盤標高:最深部EL−40m・
左岸翼頂部EL25〜35m
・右岸翼頂部EL50〜90m)